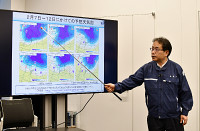江戸川をつくる人 第3回 江戸川総合人生大学卒業生・井上憲一さん
江戸川区北小岩には、弥生時代後期に人々が集落で生活していた証拠の裏付けとなる「上小岩遺跡」が存在する。同遺跡は1952(昭和27)年、当時小岩第三中学校に在籍していた生徒が自宅裏の用水路から数個の土器片を発見し、同校担任教教諭・中村進さんに連絡したところから始まる。中村さんは採集と研究を始め、およそ35年間にわたる同遺跡採集調査の中で、延べ2万8700点に及ぶ遺跡・土器破片を発掘した。


区立上小岩小学校の校舎改築工事に伴い、2020年以降新たに6~8世紀の住居跡と見られた遺構が発見され、郷土資料室で展示会が開催されるなど再度注目が集まっている。遺跡以外にも、1877(明治10)年の大皐越で北小岩地域が困窮の際、私財を投じて圦樋(いりひ)を整備し人々を救った石井善兵衛さんの功労碑や、古くからある寺院など数々の文化財も保有している同地区。この文化・史跡に大きな価値を感じ、江戸川総合人生大学で2年間学んだ井上憲一さんは、在学中だけでなく現在も、上小岩の史跡について独自の研究を続けている。

――江戸川総合人生大学で学ぼうと思ったきかっけは?
江戸川区にこの大学があることは以前から知っていました。中学時代の同級生が国際17期生にいて、私にここで学ぶことを勧めてくれたのがきっかけです。もともとライフワークとして北小岩の歴史・文化を調べていたので、まちづくり学科なら生かせるのではないかと考えたのです。
――この土地で生まれ育ち、まちをずっと見てきた井上さんならではの視点や思いがありますね。2年間の授業の中で、さらに研究を深めていったのですね。
より多くの人に、この地域の歴史や文化を知ってもらい、継承していきたい。未来を生きる子どもたちのために、自分は何ができるだろうと考えました。

――手製の地図や卒業発表の資料など、全てに見応えがあります。特に「北小岩への招待状」は文化財の説明に全てQRコードが付いていますね。
研究の中で北小岩地区の文化財とそれぞれの案内板(18カ所)を調べ直しました。区立中央図書館には多くの書籍があるので、足を運びながら文献を参考にしました。史跡巡りで訪れる観光客や、小さな子どもでも理解できるようにQRコードを作ってみたのです。コードを読み込むと、自動音声や写真のスライドが再生される工夫をしています。QRコードはほかの発表資料にも添付しています。

――再生してみると、ゆっくりとした自動音声と画像でとても分かりやすいです。イチョウの高さや色付く様子なども、子どもたちが見てもよく理解できそうです。文字だけでは伝わらないこともありますね。
何よりも興味を持ってもらうことから始まるかなと思います。そのために、視覚に訴えていく資料には意味があるように感じます。

――大きな研究発表資料「北小岩の知られざる功労者」の中村進さんや石井善兵衛さんにもコードが添付されていますね。石井善兵衛さんは明治時代の北小岩地区を干ばつから救ったヒーローのように見受けられます。
そうです。北小岩8丁目の親水緑道の起点に「水神碑」がありますよね。明治時代、上小岩・中小岩・小岩田・伊与田の4村で農作業を生業としていたこの地域は、しばしば十分な水が得られないことで困窮生活を送っていました。そこに、江戸川の水を引き入れたり、出したりする水門の樋(トンネル状の樋管)を作ったのです。
 ――今でも、この辺りを散歩すると親水緑道に出合えますが、この樋の名残なのでしょうか?
――今でも、この辺りを散歩すると親水緑道に出合えますが、この樋の名残なのでしょうか?
1878(明治11)年に完成した時には「共和圦樋(いりひ)」と呼ばれていました。その後、東京府知事によって「善兵衛樋」と命名され、用水網を形成していったのですが、1967(昭和42)年の河川改修時に多くの用水路は消滅してしまいました。一部「仲よしこみち」として整備され現在も生かされているところもあります。この地域の親水緑道は、ただの遊歩道ではなく善兵衛さんの功績の名残なのです。歩いてみると楽しい発見がいろいろあります。
 ――この資料を拝見しながら私自身初めて知ることも多く、とても勉強になります。そのまま教材として生かせそうにも思えます。
――この資料を拝見しながら私自身初めて知ることも多く、とても勉強になります。そのまま教材として生かせそうにも思えます。
昔を知ることや、自分たちの暮らしている土地の歴史を知ることが、まちへの関心につながったり、生まれ育った地元を好きになったりという気持ちを生むのでは、と考えています。ここで育った子どもたちに郷土愛を持ってもらえたら。同時に、素晴らしい文化財や史跡があることを知り、誇らしい気持ちを持ってもらえたら、こんなにうれしいことはありません。
――今後の井上さんがさらに取り組んでいきたい研究や展望などあればお聞かせください。
多くの人が、もっと手軽に地元の文化財や史跡について触れる機会が増えていけばいいな、という思いがあります。現在、文化財には案内板も設置されていますが、30年以上前に建てられたもので文字の記載のみ。練馬区では文化財の案内板にQRコードが設置されていて、こうした形で江戸川区でも普及していったらいいですね。上小岩遺跡についても、常設展で目に触れるところがあるだけでも、関心度が高まるのではないかなと。未来を生きる子どもたちに文化継承し、郷土愛を育んでもらえたら。

――貴重なお話と研究発表をありがとうございました。
大きな手製の資料を手に、インタビューに答えていただいた井上さんの目は未来に向けて優しく輝く。現在、新たに「佐倉街道」に関する調査を始めているという。江戸川総合人生大学での2年間の学びと郷土愛を胸に、地域のために研究を続ける井上さんのライフワークはこれからも続く。